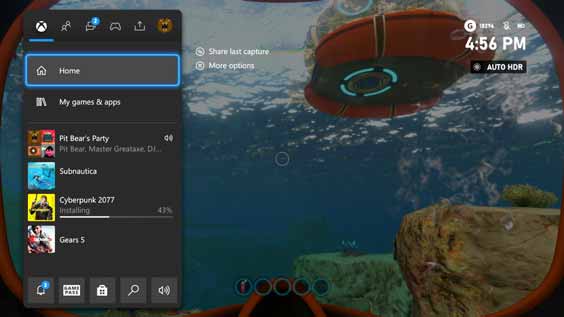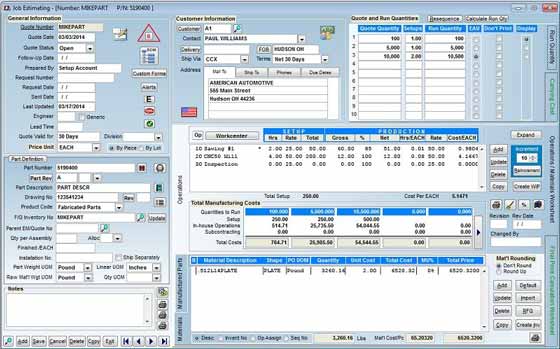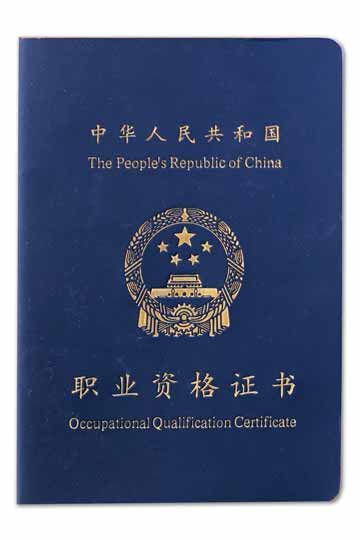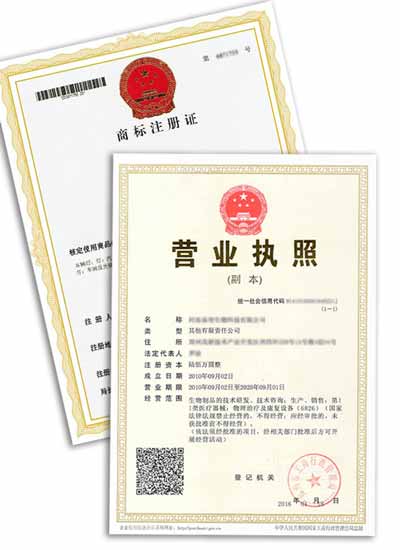文化与资讯
翻译语种
联系我们
邮箱:liwei@bowwin.com
手机:+86-18565641179
电话:+86-755-8304 2538
地址:深圳市福田区彩田路彩虹新都彩霞阁23A
翻译资讯
各国名家谈翻译:翻译就像是什么?
作者:admin 发布时间:2013-12-09 16:31点击:
2013年12月9日,据博文专业翻译公司了解到,看过翻译者写出的内容,常会把他们比作演员或演奏家,这被认为是极为妥当的比喻,毕竟都有脚本或乐谱,在以自己的理解来再现原文这点上,翻译与演技、演奏有着极大共同点。下面是日中对照版各国名家谈翻译:
みなさまは翻訳あるいは翻訳者を何に例えますか?
大家会把翻译或者说翻译者比作什么呢?
翻訳者が書いたものを読むと、翻訳者は俳優や演奏家に例えられることが多いようです。これは至極順当な比喩と言いますか、元となる脚本や楽譜(=原文)があり、それを自分なりに解釈しながら再現するという点で、翻訳と演技や演奏は大いに共通しています。
看过翻译者写出的内容,常会把他们比作演员或演奏家,这被认为是极为妥当的比喻,毕竟都有脚本或乐谱(=原文),在以自己的理解来再现原文这点上,翻译与演技、演奏有着极大共同点。
今回は、私が個人的に気に入っている、翻訳に関するアクロバティックな(?)比喩をご紹介します。
本次我就来介绍个人中意的对翻译的惊险(?)比喻。
·器とその破片
·容器及其碎片
ベンヤミンという哲学者は、原文と訳文を、器の破片に例えています。
有位叫本雅明的哲学家把原文和译文比作容器的碎片。
「ひとつひとつの破片は同じ形ではないものの、もとの器(=原文の内容)を表すものでなければならない」という意味だと私はとらえています。ここでベンヤミンは聖書の翻訳を念頭に置いていますが、この比喩は実務翻訳にもヒントを与えている気がします。
我把这理解为“一块一块的碎片尽管形状不同,但是都必须要表示原本的容器(即原文内容)”。本雅明在此是以圣经翻译为例来说,不过这一比喻对于做翻译的人也有提示作用。
ひとつの器の破片が組み合わせられるためには、二つの破片は微細な点にいたるまで合致しなければならないが、その二つが同じ形である必要はないように、翻訳は……愛をこめて微細な細部に至るまで原作の言い方を翻訳の言語のなかに形成し、そうすることによってその二つが、ひとつの器の破片のように、ひとつのより大いなる言語の破片として認識されるのでなければならない。
一件容器的碎片若要重新拼在一起,就必须在极小的细节上相互吻合,尽管不必相互相像。同样,译文……要周到细腻地融会原文的意指方式,从而使原文和译文成为一种更大语言的可辨认的碎片,恰如容器的碎片是容器的组成部分一样。
——ヴァルター·ベンヤミン「翻訳者の使命」
——瓦尔特·本雅明《翻译者的任务》
·硬貨
·硬币
村上春樹は分かったような分からないような、でも何とも印象的な比喩で知られます。そのなかでも、翻訳を硬貨になぞらえるこの比喩は、翻訳を仕事にするようになってからより一層思い起こすようになりました。
村上春树因似是而非却又无比印象深刻的比喻而知名。当中尤以把翻译比作硬币的比喻,我在从事翻译工作后尤其令我容易想起。
僕は必要経費で買い込んだ二つの書類棚を机の両脇に置き、左側には未訳の、右側には翻訳済みの文書を積み重ねた。
我用必备品经费买来的两个文件柜置于桌子两侧,左侧放未译的,右侧放译毕的。
文書の種類も依頼主も実に様々だった。ボール·ベアリングの耐圧性に関する「アメリカン·サイエンス」の記事、一九七二年度の全米カクテル·ブック、ウィリアム·スタイロンのエッセイから安全カミソリの説明文に至る様々な文書が「何月何日まで」という荷札を付けて左側の机に積み上げられ、しかるべき時の経過を経て右側に移った。そして一件が終了する度に親指の幅一本ほどのウィスキーが飲み干された。
译件的种类也罢委托人也罢委实多种多样。有《美国科学》上刊载的关于滚珠轴承耐压性的报告,有1972年度全美鸡尾酒专刊,有威廉·斯坦劳的小品文,有安全刮须刀说明书。凡此种种,一律贴上期限日期标签堆在桌子左侧,经过一段时间后移到右侧。每译完一份,都要喝掉大拇指那么高的威士忌。
考えるに付け加えることは何もない、というのが我々の如きランクにおける翻訳の優れた点である。左手に硬貨を持つ、パタンと右手にそれを重ねる、左手をどける、右手に硬貨が残る、それだけのことだ。
搞我们这个档次的翻译的好处,就是无须加进什么想法。左手拿硬币,啪一声放到右手,左手腾空,右手留下硬币,如此而已。
——村上春樹「1973年のピンボール」
——村上村树《1973年的弹子球》
改めて読むと、1970年代の翻訳会社の描写が妙にリアルなことに驚きます。今の私にはこの比喩の“軽やかさ”が自分の課題だと感じます。ぱたんと硬貨を返すように軽やかに訳す。しかし「我々の如きランク」の翻訳者としては、これがとても難しいのです…。
重读下来,我对1970年代翻译公司的描写之真实而惊讶。如今我的问题就在这一比喻的“轻快”上面。如同翻转硬币般驾轻就熟的去翻译,不过作为“我们这个档次”的翻译那是相当的困难……
·宙づり
·悬空
以下は例えというよりは説明なのですが、個人的に非常に共鳴する翻訳者の定義です。
豊崎光一というフランス哲学者によるものです。
下面的说是例子不如说是说明,是让我本人有强烈共鸣的对翻译者的定义。
这就是名为丰崎光一的法国哲学专家下的定义。
究極的には、私が翻訳者と呼ぶのは一個の職業であるよりも、世界を生きかつ見る一つの流儀です。それは根付くのを拒否すること、二つの中間に意志的にとどまることであります。……もし翻訳者の、翻訳という実践の倫理とでもいうべきものがあり得るとしたら、そう、私にとってそれはこの拒否、翻訳者がまったく自発的に引き受けるこの宙づりの状態の中にしかありません。
说得极端点,我认为与其把翻译者看作一种职业,不如说是存在并观察世界的一种做派。抗拒生根,而以个人意志停留在两者之间。……如果说翻译者有可称为翻译实践伦理的东西,对我来说那也只会存在于这一抗拒、在以翻译者纯粹的自主接受的这一悬空状态当中。
——豊崎光一「翻訳と/あるいは引用」
——丰崎光一《翻译与/或引用》
翻訳者は、日本語の端に立って中を眺めている、転校生のような感覚になることがよくあります。「中間に意志的にとどまる」「宙づりの状態」という言葉はこの、端から眺めている感覚を言い当てているように思います。
翻译者站在日语一侧眺望当中,这常让人有种转校生的感觉。我认为“以个人意志停留在中间”“悬空状态”的描述说的就是从一端眺望的感觉。
あるいは、翻訳者は子供に地図を描いて渡しておつかいに行かせ、電柱のかげから見守っている母親のようだとも思いますが(地図が訳文、子供が依頼者)、この、自分が直接当事者になれない感覚を指して「宙づり状態」と言っているような気もします。
也有说翻译者就像母亲,画了地图交给孩子让他买东西,然后躲在电线杆后面守候着(地图是译文,孩子是委托人),“悬空状态”说的就是自己无法成为直接当事人的感觉。
·棒高跳び
·撑杆跳
文芸翻訳家の鴻巣友希子氏は『翻訳のココロ』というエッセイ集のなかで翻訳をさまざまに例えていますが、なかでも印象的なのが棒高跳びの例えです。こちらは硬貨の例えとは対照的に、教科書のようにきれいな比喩だと思います。
文艺翻译家鸿巢友季子在《翻译之心》这本文集中,用了很多东西来比喻翻译,当中给我印象最深的是撑杆跳的例子。这与硬币的比喻正相反,是教科书般漂亮的比喻。
翻訳は棒高跳びに似ている。という気が少ししてきた。ふくまれる意味の伝達というバーを越せなければ、そこで敗退であり、だが、文中密かにくだぐだしい解釈をもりこんでバーより高く跳びすぎては、力の無駄づかいであるし、第一にみっともない。やはり、ほどよい余裕でクリアするのが美しい。
我逐渐觉得翻译与撑杆跳相似。如果不能跨越传达出所含意思这一高杆就算失败,然而,如果暗中絮絮叨叨的过多解释,跳的高出杆太多,那不但白费力气,也不中看。还是要跨越得迎刃有余而又恰到好处最漂亮。
——鴻巣友季子「ホンヤク棒高跳び」p16-17
——鸿巢友季子《翻译撑杆跳》p16-17
このエッセイが収められた「翻訳のココロ」のなかでは、柴田元幸様との対談があり、そのなかで翻訳を何にたとえるかという、そのまんまの話題が展開されています。
收录该文章的《翻译之心》里还有与柴田元幸老师的对谈,当中就有对翻译比作什么这一话题的展开。
柴田:翻訳とはどういうものか、っていう喩えを見ると、そこにけっこう個性が出ると思って。鴻巣さんの言うことって人間的ですよ。あの、「あくを抜く」とかさ。
鴻巣:ああ。
柴田:まあ、「棒高跳び」でもそうなんですけど。そういう、人がやることに喩えますよね。
そういうのってあんまり実は聞いたことがないような気がする。少なくとも僕は翻訳というのは圧倒的にオーディオアンプだと思っているし、岸本佐知子さんはもっとわけのわかないことを言って、「甕(かめ)に水を張ってゴーンと叩くとこれが翻訳だ」なんて。なんかわけのわからない(笑)。……それは「あくを抜く」と本当は同じなんだけど、翻訳者岸本さんはそれを張った甕になるんですよね。
鴻巣:あ、その甕になることが翻訳だと。
柴田:そう、それでその甕が鳴るんですよね、叩かれて。それが訳すことなんだと。よくわかんないんだけど(笑)。でも僕も、アンプになるとかね、あんまり人間に喩えないんですよね。そこはけっこう大きな違いじゃないかなと思ったんですよね。オーディオアンプも面白いですが、甕だなんて(笑)。
柴田:来看看对翻译为何物的比喻,有很多独具个性的例子。鸿巢老师说的都很人化,比如“不俗气”什么的。
鸿巢:恩。
柴田:“撑杆跳”也是,都是比喻人们会去做的事情呢。
像这些实际上感觉都没怎么听过,至少我是觉得翻译肯定是扩音器,而岸本佐知子老师更甚,说是罐子里装水再咚的敲响,这就是翻译什么的。让人摸不着头脑(笑)……这跟“不俗气”在本质上相同,但是翻译家岸本老师比作装满水的罐子呢。
鸿巢:啊,变成罐子比作翻译。
柴田:没错,罐子敲了会响吧,她说这就是翻译。我倒不是很懂啦(笑)。不过我也比喻成扩音器这种不太人化的东西。其实这当中也没有太大的不同啦。扩音器也挺有意思的,什么罐子嘛(笑)。
柴田元幸様の発言に触発され、わたしも翻訳を何かに例えてみたいと思います。
受到柴田元幸老师发言的触发,我也想试试把翻译比作什么。
·奴隷
·奴隶
翻訳者は奴隷だと私は思います。と言うときっと誤解されると思うので説明しますと、翻訳が奴隷労働だという意味ではありません。
我认为翻译者是奴隶。这么一说肯定会被误解,再说明下,这并非说翻译是奴隶般的劳动。
そうではなく、「奴隷は主人の頭で考える」という意味において、翻訳者は奴隷なのです。
自分の思考がなくなって、ご主人様(=原文の書き手)の思考回路で訳すさまが奴隷だと思います。自虐的に解釈されることは百も承知なのですが、そこは意図していません。
ところで、古代ローマにおいて翻訳は奴隷の仕事だったそうです(出典不明)。
这是从“奴隶是顺着主人的想法去思考”这层意思出发,才说翻译者是奴隶。
丧失自己的思考,而根据主人(原文写作者)的思考回路来翻译,我觉得这就是奴隶。我当然十分清楚这是自虐式的解释,不过并非我有意为之。
不过,据说在古罗马翻译就是奴隶的工作(出典不明)
·小人の靴屋さん
·小矮人鞋匠
人が休んでいる間に仕事し、翌朝には何事もなかったかのようにきれいに靴(=訳文)ができている。実務翻訳者は小人の靴屋さんだと言えます。同じ路線の比喩として翻訳者は「打ち出の小槌」とも言えます(翻訳者が小槌、訳文は小判)。どうやら私は「翻訳者は努力の跡を見せてはいけない」と思っているようです(?!)
在别人休息时工作,翌日早晨做好漂亮的鞋子(译文),仿佛什么都没发生过,所以我说从事翻译的人是小矮人鞋匠。同一思路的比喻也可说翻译者是“百宝槌”(翻译者是小槌、译文是金币)。看来我是觉得“翻译者不能让自己的努力示人”(?!)
·植木職人
·花匠
翻訳者は植木職人、原文はぼさぼさの木、訳すのは木を刈り込む作業です。原文は多義性を持つことがままありますが、翻訳においても同じように多義性を持たせようとすると、たいていは意味不明になります。訳(=刈り込まれた状態)をつくるには、残すべき枝を判断し、落とすべき枝(けっこういい枝もあったりしますが)は思い切って切り落とす必要があります。
翻译者是花匠,原文是乱蓬蓬的树,翻译是修剪枝叶的工作。原文常带有多义性,如果在翻译中也欲使其带上多义性,则多会变得意义不明。要翻译(=修剪后的状态)就要判断需留下的枝叶、要剪除的枝叶(当中也有相当好的)就得下狠心剪除。
·海女さん
·渔女
私が実際に訳していて最もよく想起するのは、海にもぐるイメージです。翻訳者は「この書き手はなぜこう書いているのだろう?」と考え、書き手の心の奥深くまで分け入っていくことがあります。たとえ契約書や論文のような硬い文章でも、書き手にその言葉を選ばせた心理がわからないと、訳語が出てこない場合はけっこうあります。字面に表れない心理を探るとき、私は海を深く潜っていくような心境になります。海の底にあるひとつの石を拾いにいく作業の繰り返しが翻訳だと思います。
我在实际翻译当中最常想起的是潜入海中的场景。翻译者会思考“这位作者为什么这样写呢?”而深入到原作者的内心里去。即便是合同、论文等生硬的文章,如果不能理解作者选词用句的心理,有时就想不出合适的对应表达。在探寻不外露在字面上的心理时,我会有仿佛潜到深海中的心情。所以我认为翻译就是到海底去捡一块石头的工作的重复。
【温馨提示】如您遇到翻译困难或者有翻译需求,不妨拨打博文翻译公司全国服务热线:400-88-13580(一生我帮您!)我们将为您提供专业的翻译解决方案,免费稿件质量评估。
- 上一篇:义乌已发放首张外贸翻译从业证
- 下一篇:亚洲企业并购“有些内涵是无法翻译”
文化与资讯
-
2022-10-26选择北京翻译公司要注意哪些问题?
-
2021-06-22陪同翻译有哪些注意事项?
-
2021-01-20爱丽丝·门罗:不是“蛮译”是“慢译”
-
2021-01-18翻译公司:只是翻译惹的祸
-
2021-01-03常用网上资源
-
2021-01-03英伦印迹:看我这样享受恬淡留学生活
翻译服务